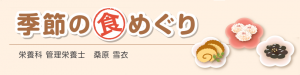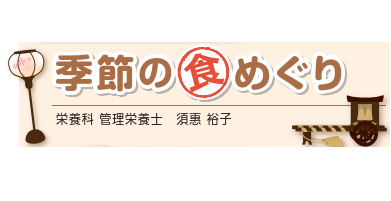
3月3日は五節句の一つ「上巳(じょうし・じょうみ)の節句」別名「桃の節句」「ひな祭り」です。今回は、ひな祭りにまつわる食べ物について紹介します。 ※それぞれ諸説あります

菱 餅
下から「緑・白・桃」の三色の餅を重ねたものが定番です。ひし形は、魔よけの力があるといわれるヒシの実をモチーフにしたもの。緑色は大地、白色は雪、ピンク色は桃を表し、雪の下に新芽が芽吹いて、桃の花が咲くという意味があります。緑色▷健康や長寿、白▷清浄、ピンク▷魔除けの願いがこめられているともいわれています。
ひなあられ
関西地方では丸形のしょっぱい&甘いあられ、関東地方では米粒型の甘いポン菓子、と味や形が異なります。
ちらし寿司
ちらし寿司そのものにはいわれはありませんが、縁起の良い具材がお祝にふさわしいとされているようです。
●え び・・・・・腰が曲がるまで体が丈夫という意味で長生き
●れんこん・・・ 複数の穴が開いていることから、将来が見通せる
●豆・・・・・・ マメにはたらく
はまぐりのお吸い物
はまぐりは二枚貝で、対になっている貝殻同士しかピッタリ重ならないので、何事にも相性のよい相手と結ばれて、仲睦まじくすごせるようにとの意味があります。